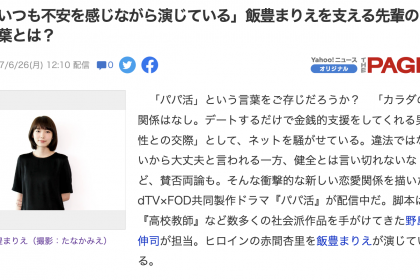ひと図鑑 越川慎司さん(日本マイクロソフト業務執行役員)
日本マイクロソフト株式会社業務執行役員越川慎司さん。このたび、「幸せと成果を両立する『モダンワークスタイル』のすすめ 新しい働き方」という書籍を上梓されました。この本は、真の働き方改革とは何かということを、越川さんご自身の経験を基に、具体例を交えてわかりやすく書かれています。自らの幸せと求められる成果の両方を手に入れることは本当にできるのでしょうか? 越川さんにお話を伺いました。
 日本マイクロソフト株式会社執行役員Officeビジネス責任者。国内通信会社、米系通信会社、ITベンチャーを経て、米マイクロソフトに入社。11年にわたり、製品の品質向上プロジェクトの責任者CQO(Chief Quality Officer)やOfficeビジネス責任者を務める。1年間に地球を5〜6周するほどの海外出張の傍ら、国内では多数の講演などをこなすという、時間と場所の制約を受けず、幸せを感じながら成果を残す働き方(モダンワークスタイル)を実践している。
日本マイクロソフト株式会社執行役員Officeビジネス責任者。国内通信会社、米系通信会社、ITベンチャーを経て、米マイクロソフトに入社。11年にわたり、製品の品質向上プロジェクトの責任者CQO(Chief Quality Officer)やOfficeビジネス責任者を務める。1年間に地球を5〜6周するほどの海外出張の傍ら、国内では多数の講演などをこなすという、時間と場所の制約を受けず、幸せを感じながら成果を残す働き方(モダンワークスタイル)を実践している。【『新しい働き方』内容紹介】
「働き方改革」が政治・行政、企業経営上の重要課題となり、ブームのような様相を呈しています。しかし、いち早くテレワーク等の仕組み
 を導入、経営の効率化・業績向上・離職率低減を実現し、さらには優秀な女性の転職希望が殺到するまでになった日本マイクロソフトの業務執行役員である著者は断言します。「働き方改革は失敗します」と。5年間で80万人がオフィス見学ツアーに参加し、その仕組みからオフィス運営まで注目の的となり、「ワークスタイル変革の聖地」とまで呼ばれる同社。ハード/ソフト両面での成功の秘密を、国内外の多様な企業に勤務した経験もある立場から懇切丁寧に解説します。また、著者自身、母親の介護を抱えながら、1年で地球を5~6周もするような超多忙な仕事ぶり。かつ、外資系企業で重要なポジションを担うことからくる重責とハードワークにもかかわらず、ワークライフバランスの高い生活を維持できているのはなぜなのか──。そのすべてを、日本マイクロソフトの社員として、また一個人としての視点から明します。自らの可能性を高める効率的な働き方を目指すビジネスマン個人、また、各企業の「働き方改革」担当者、必読の1冊です。(amazon.co.jpより)
を導入、経営の効率化・業績向上・離職率低減を実現し、さらには優秀な女性の転職希望が殺到するまでになった日本マイクロソフトの業務執行役員である著者は断言します。「働き方改革は失敗します」と。5年間で80万人がオフィス見学ツアーに参加し、その仕組みからオフィス運営まで注目の的となり、「ワークスタイル変革の聖地」とまで呼ばれる同社。ハード/ソフト両面での成功の秘密を、国内外の多様な企業に勤務した経験もある立場から懇切丁寧に解説します。また、著者自身、母親の介護を抱えながら、1年で地球を5~6周もするような超多忙な仕事ぶり。かつ、外資系企業で重要なポジションを担うことからくる重責とハードワークにもかかわらず、ワークライフバランスの高い生活を維持できているのはなぜなのか──。そのすべてを、日本マイクロソフトの社員として、また一個人としての視点から明します。自らの可能性を高める効率的な働き方を目指すビジネスマン個人、また、各企業の「働き方改革」担当者、必読の1冊です。(amazon.co.jpより)Q. 苦労されて本を書き上げられた今のお気持ちを教えてください。
この本を書くことで、働き方はもとより自分の生き方についても深く考えていたことに気づきました。母は、私を出産したときのダメージが今も残ってしまっています。双生児だった兄はこの世に生まれ出ることはありませんでした。そのことで、何をするときも「充実した人生を送りたい」「より成果を残したい」「幸せを感じていたい」という気持ちがいつも根本にあったと、社会人になって20年経った今、感じています。
今回、改めて考えてみて、「満たされているかどうか」「思い通りに生きているかどうか」こそが「幸せ」ということではないかと感じています。例えば英単語を一つ覚えるにしても、目標を持って取り組めば、達成したときに幸福感を感じられるはずです。それが、仕事上のプロジェクトやイベントであったり、数千億のビジネスだったりすれば、より強く幸福感が感じられるはずです。また、それをチームメンバーや社外のかたと共有することができれば、その幸せは何倍にも膨れあがることもわかりました。そのことが私にとっての一番の幸せです。
企業に所属していて難しいなと感じることのひとつは、文化の壁です。企業のなかには、さまざまなバックグランドで育って来た人たちがいますから、育児にしても介護にしても、「早く帰れていいな」と思う人もいれば、「後ろめたい」と思っている人もいます。しかしそこには、企業ではなく、周りの人たちの気遣いや同僚や部下が幸せに感じることへの共感というものが大きく影響していると思っています。
なぜなら、企業が個人の幸せを実現してくれるわけではないからです。企業の役割は、あくまでも個々人が幸せを達成できるようにサポートすることなのです。しかし一方で企業が制度を作るときは、往々にして、対外的なアピールになったり、制度を作ること自体が目的になってしまったりするため、実現手段にばかり目が行きがちで、個人の幸せが置き去りにされてしまうこともあります。
 確かに、女性の離職率は40%改善しましたが、まだまだ改善の余地はあると思っています。私の部下は、半分以上が女性ですし、週3回在宅勤務をするメンバーも複数名います。小さい子どもがいる男性社員もいます。私自身も介護をしていますから、メンバーの誰もが在宅勤務や休みが取りやすい環境を作っているつもりです。
確かに、女性の離職率は40%改善しましたが、まだまだ改善の余地はあると思っています。私の部下は、半分以上が女性ですし、週3回在宅勤務をするメンバーも複数名います。小さい子どもがいる男性社員もいます。私自身も介護をしていますから、メンバーの誰もが在宅勤務や休みが取りやすい環境を作っているつもりです。
つい先日のことですが、「子どもが生まれたばかりの男性社員が19時くらいにこそこそと帰って行ったよ」と、上級役員に聞かされました。今の制度では、早く帰ることに後ろめたさを感じる必要はまったくないはずにも関わらず、彼にそう感じさせてしまったことにとてもショックを受けました。彼はとても優秀な社員ですし、お子さんの夜泣きで夜中にたびたび起こされていることも、早く帰った日は夜寝る前にメールの返信をしていることも知っています。またそんな状況でもしっかり成果をあげています。マネージャーとして、そういう彼をしっかり見ていることを伝えたうえで、早く帰ることに後ろめたさを感じる必要はないと伝えました。おそらく、そういった一つひとつが企業文化を変えることになるのではないかと思うのです。
彼に確認すると、寝る前にメールを返信した方がゆっくり寝られるし、朝もさわやかに過ごせるということだったので、5分や10分だったら夜中に仕事をしてもいいんじゃないかと伝えました。でももし、それが彼にとってストレスになるならば、絶対にやめるべきだと思います。
あくまでもその人がやりたいことを、自分のペースでやりたいときに仕事ができることが大事なんだと思うんですね。働きたいのに働けないということがストレスになるのは間違いありませんから、社員が働きたいときに働けるようにするというのが企業の役割だと思っています。
週休3日ということは、働かない時間を作るのではなく、社員に時間の自律性を意識しなさいということではないでしょうか。毎年売り上げを上げ続けるかつ働かなくてもいいという時間を増やすということは、働いてもいいという時間のなかで効率的にアウトプットを出さなくてはなりません。それには自分を律する力が必要になります。おそらくそれは9時から5時半まで机の前に座って仕事をするよりも大変なことだと思うんですよ。
私自身にとってもより多くのことを達成する「アチーブモア」は、大きなチャレンジのひとつだからです。仕事で成果をあげることはもちろん、プライベートでも、映画を観て誰かと共有したい、素敵な音楽を聴いてリラックスしたい、友人と話をして共感したいなど、プライベートでもやりたいこと山ほどありますから、そのために「アチーブモア」は欠かせないんです。
実は先日の休暇に、自分のやりたいことを書きだしてみたのですが、まだまだ実現できていないことがたくさんありました。私は家事もしますが、どうやったら効率的にできるかをいつも考えています。それまでよりもうまく掃除ができたり、食器洗いが終わったりすれば、使える時間も増えますから、その時間は自分へのご褒美の時間に使っています。その時間をどんどん貯めれば、映画を観に行く時間もできますよね。会社以外の普段の生活のなかでも、工夫して時間を捻出することで、人や社会とより繋がっていくことができると思うんです。
 人の性として「妬む」「嫉む」というネガティブな感情を抑えるのは難しいことですから、ある意味、鈍感力や割り切りが必要なのではないかと思いますね。日本の社会全体が、いろいろなシーンで人を競わせるようになっていますから、あえてそれに乗らないようにすることも大切なのではないでしょうか。
人の性として「妬む」「嫉む」というネガティブな感情を抑えるのは難しいことですから、ある意味、鈍感力や割り切りが必要なのではないかと思いますね。日本の社会全体が、いろいろなシーンで人を競わせるようになっていますから、あえてそれに乗らないようにすることも大切なのではないでしょうか。
「勝ちたい」「負けたくない」という感情を持つこと自体は悪いことではありませんけれど、隣の人の成功を妬む、足を引っ張るなどは、誰にとっても決してプラスにはなりませんからね。もし妬まれたり、嫉まれたりする立場になったら、ぜひ自分のなかの価値観を大切にしていただきたいですね。成功することは素晴らしいことですから、自分でしっかりと認めてあげてください。
大フィーバーが起こるような大統領や首相であっても、必ず数パーセントの反対派の人はいるわけですから、全ての人に好かれたり、気に入られたりすることは、この競争社会のなかにあっては難しいと思いますね。
何よりお伝えしたいのは、「目的と手段を取り違えないでください」ということです。手段が目的になってしまうことが多いと、それは人間関係の亀裂や精神的なストレスを生み出します。そうならないためには、まずは何をゴールとするのかを見つめ直してほしいということが大きなメッセージです。
私が考えるゴールは、人生を生き抜くことです。そのための手段が「働く」ことだとしたら、「働く」ことに対する考え方をこの機会にもう一度考えてみてほしいと思います。そうすることが、人生を生き抜いて幸せになることに繋がるというのが、私の体験を通したメッセージでもあります。
残念ながら、旧態依然の固定的な観念を持ったかたもまだお見かけすることがあります。しかし、そういうかたにこの本を読んでいただくことで、少しでも化学反応が起きてほしいと思っています。また、本を読んで「働く」ことに対する考えを変えて、自信を持って成果をあげるかたたちが増えれば、企業のなかの文化も変わっていくでしょう。そのかたたちがイノベーターになれば、必ず企業も変わっていきますから、日本も欧米や中国、韓国に負けない経済力を持てるようになることを期待しています。
越川慎司さんとお話しして
越川さんは、1年の大半を出張や講演会などで日本のみならず世界中を飛び回っていらっしゃいます。おまけにご家族の介護、家事までこなしているというから驚きです。でもお会いしてもその大変さは微塵も感じさせません。それは、自分を律し、時間を律する強さに裏付けられているからに他ならないのだと思います。
働き方改革をテーマに本を作ろうとお話ししてちょうど1年。ようやく形になりました。越川さんの経験と想いがたくさん詰まったこの本をたくさんの方に読んでいただきたいと思います。越川さんが願う「年齢や性別、国籍を超えて、働きたいと思う人が思う存分に働ける環境、そしてその価値を見いだしてくれる社会」が遠くない将来に実現しますように。